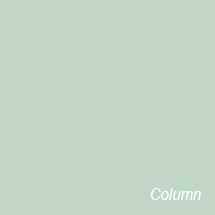| 年月日 |
タイトル |
執筆者 |
| 2017/01/01 |
富士山で観測をしたくなるのはなぜなのか?加藤俊吾 (首都大学東京)
私が富士山観測にかかわりを持ちはじめたのは2005年ごろからのようです。かなりの頻度で開かれていた富士山高所科学研究会に参加したり、2005年のゴールデンウィークには… |
 |
| 2016/01/08 |
富士山頂で上空の化学反応を調べる緒方 裕子 (早稲田大学創造理工学部)
筆者の所属する研究室では、毎年夏季(7-8月)に1-2週間程度の集中観測を、富士山頂、富士山麓太郎坊、早稲田大学の3地点で同時に行っている。… |
 |
| 2015/01/01 |
富士山頂で新たな伝説をつくる鴨川 仁(東京学芸大学)
山岳小説で名高い新田次郎氏が描く小説でも富士山は格別な題材であろう。このことはご本人が富士山測候所に勤務し、レーダー設置の中心人物であったため … |
 |
| 2014/01/01 |
自然が先生 富士山頂で教材づくり古田 豊(立教新座中学校・高等学校)
富士山頂の自然を観照したい。理科実験を通して自然の振る舞いを探るには、どのような実験を工夫したらよいか。日本最高峰の地で行う実験と同じ実験を学校で … |
 |
| 2013/01/01 |
雲をつかんで、微粒子の変化を調べる上田紗也子(東京理科大学)
夏季日中の富士山頂は、雲よりも上であることが多く、下方を眺めると雲海が広がることが多い。その雲海はしばしば富士山斜面に… |
 |
| 2012/01/01 |
遠くて近い富士山頂から須永温子(国立環境研究所)
「登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿」という言葉がある。言わずもがな、これは富士山のことであるが、山好きの私はこの言葉を知らなかった。… |
 |
| 2011/01/01 |
日本でいちばん高い住まいに暮らして村上祐資(東京大学)
風呂桶から溢れる湯量にしばし目を丸くする。石鹸の泡立ちが悪い。石鹸がもつ汚れ分解能力をこっちが軽くオーバーしてしまっているのだ。… |
 |
| 2010/01/01 |
宇宙に近づいて空の放射線を見張る保田浩志(放射線医学総合研究所)
ふうぅ。観測機材が置いてある1号庁舎2階へ登る階段の途中、息苦しくなって立ち止まる。富士山頂の大気圧は海抜ゼロメートルの平地に比べて65%ほど … |
 |